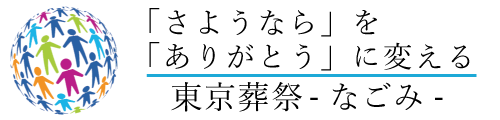供養される権利について
私たち株式会社和は、「供養される権利」という理念を軸に、すべての人が人生の最期に敬意をもって見送られる社会の実現を目指しています。
宗教や家族、経済的背景に関係なく、誰もが“供養される存在”であるという考え方を、私たちは大切にしています。
供養される権利マニフェスト
はじめに
私たちは、すべての人が「供養される権利」を持つ社会の実現を目指します。 それは、宗教や家族構成、経済状況に関係なく、誰もが人生の最期に敬意と感謝をもって見送られるべきだという、人間の根源的な尊厳に根ざした考え方です。
この言葉は、現代日本における孤独死・無縁社会・宗教離れといった現実に直面する中で、私たちが葬送の現場で感じ続けてきた「違和感」と「願い」から生まれました。
供養される権利とは何か
「供養される権利」とは、人が亡くなったあと、その人の存在が忘れ去られることなく、適切に見送られ、祈りを向けられ、敬意をもって記憶されるという文化的・倫理的・社会的な権利です。
これは法律上の制度ではなく、“生きることの延長線上にある自然な願い”です。
誰かの子であり、誰かの友であり、社会の一員として生きてきたすべての人に対し、 「あなたは確かにこの世に存在した」と伝える手段として、供養は必要不可欠な行為です。
なぜ今、「供養される権利」なのか
現代社会では、少子高齢化・核家族化・都市化・宗教離れといった要因により、 死後に適切な供養を受けられない人々が急増しています。
・孤独死を迎える高齢者 ・お墓を持たない選択をする人々 ・経済的に葬儀をあげられない家庭 ・宗教を持たないために「供養の仕方」がわからない人たち
これらの課題は、もはや個人や家族だけの問題ではなく、**社会の構造が抱える“喪失の断絶”**です。
だからこそ、私たちは「供養される権利」という言葉を社会に提示し、それを前提とした仕組み・サービス・文化の創造を進めていきます。
私たちの使命
- 誰もが供養される機会を失わない社会インフラを構築します
- 宗教や形式を問わず、個人の尊厳を守る葬送文化を育みます
- 生前から「自分の送り方」を選べる仕組み(例:信託・AIP・死後事務設計)を開発します
- 供養される権利を行政・法律・テクノロジーと連携し、制度化へ導きます
- 子どもたちが「死を遠ざけず、肯定できる社会教育」を支援します
最後に
「供養される権利」は、あなた自身のための言葉です。 あなたがこの世界に生きた証が、忘れられることなく、誰かの祈りと共に残るように。
私たちは、その小さな願いを“あたりまえ”にしていく挑戦を、今日も続けていきます。
── 株式会社 和
(発表日:2025年1月1日 / 初出:「東京葬祭なごみ」公式WEBサイト)